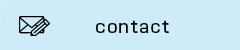-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
ウィルの太陽通信~8~
皆さんこんにちは
株式会社ウィルの更新担当の中西です。
さて今回は
~太陽光が描く2050年~
世界的にカーボンニュートラルが加速するなか、太陽光発電は再生可能エネルギーの主力として位置づけられている。
日本においても、2050年の脱炭素社会を実現するためには、太陽光のさらなる普及と技術革新が不可欠だ。
11月の静かな陽射しの中で、改めて「太陽光エネルギーの未来」を考えてみたい。
現在、太陽光発電の平均導入コストは10年前の半分以下になった。
パネルの変換効率も20%を超える製品が主流となり、建物一体型(BIPV)や農地兼用型(ソーラーシェアリング)など、多様な設置方法が登場している。
また、発電した電力を「貯める」技術も進化しており、蓄電池と組み合わせることで24時間安定した供給が可能になっている。
太陽光産業は、もはや電気を作るだけの業界ではない。
AIによる気象予測で出力を制御し、ブロックチェーンを活用したP2P電力取引が始まっている。
つまり、個人や企業が発電者となり、互いに電力を融通し合う社会が現実化しつつあるのだ。
地域単位で見ると、「エネルギーの地産地消」が進みつつある。
地方自治体が主導するソーラータウン構想や、防災拠点における独立電源化など、
太陽光は“インフラの分散化”を担う存在になっている。
特に自然災害の多い日本において、太陽光+蓄電の仕組みは非常時の命綱となる。
課題として残るのは、廃棄パネルのリサイクルと系統制約の問題だ。
今後、耐用年数を超えるパネルが増加するにつれ、回収・再利用の仕組みが重要になる。
加えて、発電量が多い昼間の電力をいかに地域全体で有効活用するか――これが次世代の課題である。
太陽光発電は「未来のための投資」であり、「地域を支える装置」でもある。
11月という節目の月に、次の10年、20年を見据えたエネルギー戦略を考えることが、
企業にも個人にも求められている。
太陽は毎日昇る。
その光を、いかに持続的な力へと変えていくか――その挑戦が、これからの社会を照らしていくだろう。