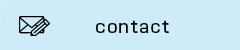-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
ウィルの太陽通信~6~
皆さんこんにちは
株式会社ウィルの更新担当の中西です。
さて今回は
~「20年後も発電させる」ために~
太陽光パネルは“メンテナンスフリー”と思われがちだが、それは誤解である。
実際には、日々の環境変化にさらされる屋外設備であり、定期点検こそが発電の寿命を左右する。
11月のように比較的穏やかな天候が続く季節こそ、保守点検に最適だ。
まず点検で注目すべきは、パネル表面の状態だ。
ガラス面の割れや欠けはもちろん、反射防止コーティングの劣化、または鳥の糞や落ち葉の付着なども発電効率を下げる要因になる。
太陽光は均一に照射されることで最大出力を発揮するが、汚れや影があると「ホットスポット」と呼ばれる局所加熱を引き起こす。
これはパネル自体の寿命を短くし、最悪の場合は発火リスクにつながる。
次に、電気系統のチェックである。
パワーコンディショナ(直流を交流に変換する装置)のファンが正常に回っているか、内部の基板にホコリが堆積していないか。
また、接続箱やブレーカーの内部で端子の緩みがないかなど、専門の計測器を用いて点検を行う。
これらは目視では判断できないが、発電データを記録しておくことで、わずかな異常も検知できるようになる。
架台の腐食やボルトの緩みも見逃せない。
特に鉄骨架台では、雨水や塩害による錆の進行が早い地域もある。
塗装補修や防錆処理を定期的に施すことで、構造強度を保つことができる。
11月の乾燥した空気は補修塗料の定着にも適しており、施工効率も高い。
また、太陽光設備は「気象データとの連携」も重要である。
最近ではAIを活用したクラウド型モニタリングシステムが普及し、遠隔で出力監視が可能になっている。
こうしたシステムでは、過去データから異常傾向を予測し、メンテナンスの優先順位を自動的に提案する機能もある。
ただし、AI任せにせず、現場での実測と併用することが理想だ。
太陽光発電は20年以上稼働させることを前提に設計されている。
しかし、20年後も同じ性能を維持できるかどうかは、日々の点検次第である。
この11月を、来年度に向けた「予防保全の月」として活用してほしい。
長く発電し続けることこそが、真の再生可能エネルギーへの投資となる。